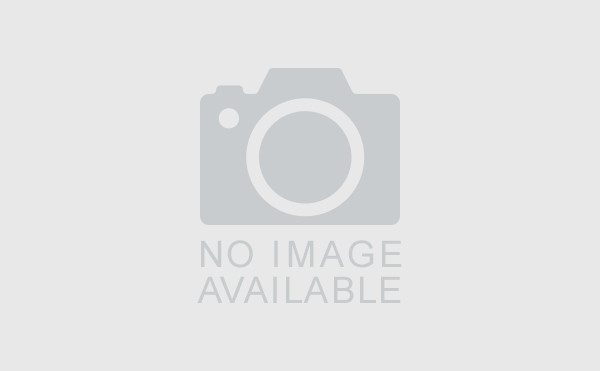中小企業でChatGPTを導入する際の注意点3選
業務に使えるAI、でも“そのまま”では危ないかも?
はじめに
ChatGPTをはじめとした生成AIは、今や誰でも簡単に使える時代になりました。
メールの下書きや提案文の作成、アイデア出しなど、中小企業の業務効率化にも大きな可能性を秘めています。
しかし、便利さの裏側には見落としがちな注意点も存在します。
今回は、中小企業がChatGPTを導入する際に特に気をつけたい3つの落とし穴を解説します。
① 入力した情報が外部に送られる? ― 情報漏洩のリスク
ChatGPTに入力した文章は、その場だけで処理されるわけではありません。
実際には、入力内容がインターネットを通じてAIのしくみ側に送られ、そこで回答が生成されます。
このため、たとえ悪意がなくても以下のような情報を入力すると情報漏洩の危険性が発生します:
- 顧客名や会社名を含んだメール文の相談
- 契約内容や社内資料の要約依頼
- 社員の個人情報や業績データの入力
特に無料版のChatGPTでは、入力データが今後のAIの学習に使われることもあり、慎重な扱いが求められます。
✅ 対策
- 機密情報は絶対に入力しない
- 実名や固有名詞は仮名・ぼかした内容にする
- 社員向けに「入力NGな情報」の例を周知する
- 必要に応じて、データが保存されないビジネス向けプラン(ChatGPT TeamやEnterpriseなど)を検討する
② 一見正しいけど実は間違い? ― 「もっともらしい嘘」に要注意
ChatGPTは、非常に自然な言い回しで文章を作ってくれますが、事実と異なる内容を含むことがあります。これを「ハルシネーション」と呼びます。
たとえば…
- 実在しない法律や制度を紹介する
- 誤った数値や統計を提示する
- ありそうな用語をでっち上げる
このような「それっぽく見える間違い」を見抜けず、そのまま社内資料や顧客へのメールに使ってしまうと、信用問題にもなりかねません。
✅ 対策
- ChatGPTの回答は**「あくまで参考・たたき台」**として活用
- 法律・制度・金額などの重要情報は必ず人間が裏取りする
- 間違いを発見したら、社員間で共有しやすい体制をつくる
③ 生成物の著作権・商用利用に注意
「AIが書いた文章を、うちのパンフレットにそのまま使ってもいいの?」
このような質問をよくいただきます。
実は、ChatGPTで作成された文章や画像の著作権・利用ルールは完全には明確でない部分もあるため、注意が必要です。
特に商用利用(ホームページ・広告・商品説明など)では以下のようなリスクが考えられます:
- 他の人も似た表現を使っている場合、盗用と誤解される可能性
- 元ネタ(引用元)がある表現を誤って無断使用してしまう
- 生成AI側の利用規約に違反してしまう場合も
✅ 対策
- 商用で使う文章は必ず人の手で最終調整を加える
- より安心して使いたい場合は、有料プランや企業向けライセンスの内容を確認する
- 気になる場合は弁護士や専門家に相談するのもひとつの選択肢
おわりに
ChatGPTは、中小企業にとって「もう1人のスタッフ」のような存在になり得るツールです。
しかし、安易な使い方や誤解したままの導入は、かえってトラブルや信用低下につながります。
Seculeafでは、生成AIを安全かつ現実的に業務へ取り入れるためのサポートを行っています。
まずは「うちの業務で何に使えるか知りたい」など、気軽なご相談からどうぞ。